親が高齢になり、将来的に実家を誰が引き継ぐのか話し合う場面は、多くのご家庭で訪れます。
その際、よく話題に上がるのが「相続」ですが、もうひとつの選択肢として「生前贈与」という方法もあります。
「生前贈与」の大きなメリットは、親が元気なうちに、自分の意思で実家を誰に譲るかを決められる点です。
受け取る側の子どもにとっても、将来の不安が軽減されることがあります。
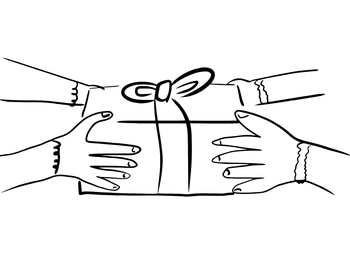
生前贈与のメリットと注意点
- 親が自分の意思で譲れる
- 受け取る側も早期に家の活用を考えられる
- 相続時のトラブルを未然に防ぎやすい
ただし、生前贈与を一部の子どもだけに話をして進めると、後々の相続時に他の相続人との間で争いになる恐れがあります。
生前贈与を検討する際は、必ず家族全員で話し合い、納得のうえで進めましょう。

また、生前贈与には「贈与税」がかかります。
贈与税は相続税より税率が高くなることが多く、特に不動産の評価額が高い場合は注意が必要です。
相続時精算課税制度の活用
贈与税の負担を抑えたい場合は、「相続時精算課税制度」の利用も選択肢です。
この制度を使うと、累計2,500万円までの生前贈与には贈与税がかかりません。
さらに、2024年からは年110万円の基礎控除も併用できるようになりました。
ただし、この制度を使った贈与分は、親が亡くなったときに相続財産として加算され、最終的に相続税の計算対象となります。
都市部以外で不動産評価額が2,500万円を超えない場合は、この制度の利用が有効です。
ただし、累計2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税が課税される点に注意しましょう。
制度利用時の手続きと注意点
相続時精算課税制度を選択すると、通常の暦年課税(年間110万円まで非課税)には戻れません。
利用する場合は、贈与を受けた翌年に税務署への申告が必要です。
不動産を贈与する場合は、登録免許税や不動産取得税も発生します。
また、生前贈与を確実に証明するためには「贈与契約書」を作成することが推奨されます。
口頭でも贈与は成立しますが、後々のトラブル防止のため、書面で残しておくと安心です。
ご実家やご自宅の承継方法は、家族構成や財産状況によって最適な選択肢が異なります。
制度の細かい条件や税金の計算方法など、専門的な部分は税理士や不動産の専門家に相談しながら、家族全員が納得できる方法を選びましょう。
元気なうちに不動産をどうするか検討を
元気なうちに、今持っている不動産をどうするか、どんな選択肢があるのか検討しておくことが大切です。
もし、想いの詰まったご実家、愛着のあるご自宅をどうするかお悩みがあれば一度ご相談ください。

このコラムを書いてくれたのは
住宅専門ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士
草野 宗徳
ファミリーラボ株式会社 代表取締役
金融商品を取り扱わない住宅専門ファイナンシャルプランナーとして中立公平な立ち位置で相談業務を行なっています。
(有)協同ホームコンサルタントとも連携し、不動産などのお悩み・お困りごとを解決します。


